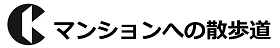マンションの仕組み(第五十五歩)
■花鳥風月 / マンションのグリーンインフラ(その1)
ある大規模マンションで「メインロータリーの高木が無残にも伐採された」との連絡がありました。伐採した理由は「木が大きくなりすぎた」だそうです。
実はそのマンションは、過去に私がアドバイザーとして係わっていたマンションでしたので見に行ってきました。
 状況は落葉広葉樹が緑地帯で2本、植升で1本の合計3本でした。切断された切り株(直径30cm超)や根張りからは、余裕で10mを超える樹高だったことが分かりました。高木ならではの根上がりは見られなかったので、きっと枝の住棟への掛かりや落葉が主な原因だと思います。しかし他の植升で育っている高木には根上がりが見られたので、今後の伐採対象だと思われました。
状況は落葉広葉樹が緑地帯で2本、植升で1本の合計3本でした。切断された切り株(直径30cm超)や根張りからは、余裕で10mを超える樹高だったことが分かりました。高木ならではの根上がりは見られなかったので、きっと枝の住棟への掛かりや落葉が主な原因だと思います。しかし他の植升で育っている高木には根上がりが見られたので、今後の伐採対象だと思われました。
本来ならば3本の高木の大きな樹冠がつながり緑のトンネルができているはずなのですが、木陰は無くなっていて、地面からの真夏の照り返しでかなりの高温となっていました。さらに、切り株の上には赤いカラーコーンが置かれている殺風景で荒れた景色に変わっていました。
アドバイザーをしている当時、「将来に渡る植栽管理の計画をしてください」と再三お願いしていましたが、建築年数が浅いファミリータイプのマンションでしたので、管理組合は初期の不具合対応で手が回らず、さらに子育て世代の若い住民が多かったために、植栽には無関心の方がほとんどでした。
木には樹齢があるので、将来の植替え計画と予算を長期修繕計画に入れる必要があるのですが、基本的な管理計画が無かったので、伐採後はシロアリを呼ぶ切り株が残されたままでした。
多くの住民の方が植栽に対して無関心で勘違いしている事は、「樹木は生活に影響が出るほど大きくならない、樹木は枯れない」だと思います。それはいつも目にしている樹木が街路樹だからです。
行政への街路樹の苦情は「信号が見えない、落葉が邪魔、陽が当たらない」等とても多く、行政はその対応で強剪定を行い、時には断幹まで実施します。そしてそれが私達の日常の景色になっています。
現在の日本で、広い庭で多くの樹木を手入れし、計画的に根回しをして移すなど「庭の景色を変える」事に費用を出す家はそう多くは無いと思います。造園業者は都市再開発や新築マンションなどの大型工事で利益を出す事になります。さらに、生活をしていくためには、年間行事である街路樹の強剪定が大事な仕事になります。その結果、造園や樹木生態を学んでいない技術の無い素人が、YouTubeなどから見よう見まねで強剪定を行うニセ庭師が増えているのが現状です。その反面、高齢化の影響で庭職・庭師と言われる伝統技術を持った職方が減少しています。「強」剪定後に「さっぱりした」との発言は庭師ではありません。樹木に適した剪定技術があって、心があるならば「きれいになった」になるはずです。
 現在のあらゆる人手不足の日本では仕方がありませんが、街路樹に限らずマンションの植栽管理でもニセ庭師を雇って強剪定をする造園業者は増えています。その理由は「庭の景色を変える」「きれいにする」のではなく、剪定回数を減らして人と時間をかけないような効率性・経済性が主になるからです。
現在のあらゆる人手不足の日本では仕方がありませんが、街路樹に限らずマンションの植栽管理でもニセ庭師を雇って強剪定をする造園業者は増えています。その理由は「庭の景色を変える」「きれいにする」のではなく、剪定回数を減らして人と時間をかけないような効率性・経済性が主になるからです。
緑に生っている「ソヨゴ」の実が赤くなる夏前に、枝ごとすべて強剪定されたのを見たことがありますが、これが現在の造園業者の現状です。春前に桜の花芽を剪定することが平気なニセ庭師です。
造園業者にとって強剪定で枯れた樹木の植替えは臨時ボーナスになります。伐採から重機での伐根、新植を重機で掘り取り、運搬して重機で植付けと、通常の人手以外の高額工事になるからです。
そのため、通常は剪定した切り口に殺菌保護剤は塗りませんので、管理組合は注意が必要です。
マンションには様々な考えの方が住んでおり、中には「樹木など最初から植えなければ問題は起きない」と言う方もいます。でもキラッキラに緑輝くパンフレットを見て、住環境の良いマンションを選んだのですから、樹木を生き物ととらえて美しく成長する姿を住民で見守ることも必要です。
前にも書きましたが、竣工時と同じ大きさの樹木を植えることは困難です。植栽計画が無いため植替える予算を計上していなければ、軽トラックで運んで人力で植えられる幼木になります。樹高はせいぜい2m程度なので下枝は残っています。しかしニセ庭師は建築限界を知らないので、草本のようにそのまま植えてしまいます。幼木時に下枝を払った結果、光合成能力が低くて樹勢の弱い樹木との長い付き合いになり、樹冠面積が大きくなるには10年以上かかります。 反面、育って下枝が邪魔になる頃に剪定すると樹木に大きな負担を与え腐朽・病気の原因になり、その後の成長は良くありません。
反面、育って下枝が邪魔になる頃に剪定すると樹木に大きな負担を与え腐朽・病気の原因になり、その後の成長は良くありません。
私たちが樹木から受ける恩恵のほとんどは樹冠が担っています。春の新緑や真夏の木陰、秋の紅葉、1年を通して移り変わる景観を楽しみたいのなら、世界と同じ樹冠率を大きく育てる計画で管理する必要があります。車道側4.5m・歩道側2.5mの建築限界を考慮して、できれば強剪定を避けて、計画的に整姿・整枝剪定で管理を行い、積極的にグリーンインフラに取組みたいものです。
次回は、マンションのグリーンインフラ(その2)について説明します。
(自然再生士/マンション管理士 福森 宏明)
【執筆者プロフィール】
福森 宏明(ふくもり ひろあき)
長年にわたり、大手建設会社で実際に多くのプロジェクトを建設してきた現場所長経験者。
清掃工場等のプラント施設や駅前の都市再開発からタワーマンション、震災後の復興支援から廃炉事業まで携わってきました。マンションでは100億円以上の団地型マンションも数件建設しています。
「環境省・文部科学省・農林水産省指定の環境教育指導者」及び1000山登山家としても活動中。
本連載では、土木・建築・造園の専門家として最新の建設技術、実際の建築現場とメンテナンス、リノベーション、住まいの安全対策、自然環境などを執筆中。
資格:一級(土木・建築・造園)施工管理技士/建築積算士・自然再生士/マンション管理士