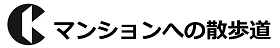マンション管理組合の財務会計(第五十三歩)
■滞納はもう怖くない!マンション管理費・修繕積立金滞納問題解決のための法的・実務的アプローチ
マンション管理士の大浦です。分譲マンション管理組合の運営において、最も身近で深刻な問題の一つが、管理費や修繕積立金(以下、「管理費等」)の滞納です。国土交通省が令和6年6月に公表した「令和 5年度マンション総合調査」によると、
5年度マンション総合調査」によると、
3ヶ月以上の管理費等の滞納があるマンションの割合は30.1%にのぼります。これは、およそ
3つの管理組合に1つが、比較的長期の滞納問題を抱えていることを示しており、決して他人事ではありません。
滞納の放置は、管理組合の財政基盤を揺るがし、マンションの資産価値を毀損するだけでなく、他の組合員との不公平感を生み、良好なコミュニティを破壊する要因にもなりかねません。
本稿では、最新のデータを基に、この喫緊の課題に対し、具体的な対応策と予防策を「3つのチェックポイント」として整理し、解説します。
なぜ滞納は起こるのか?
対策を講じる前に、滞納の原因を理解することが重要です。日本国内における包括的な滞納原因の統計データは限定的ですが、参考として、
 韓国の共同住宅における滞納原因を分析した研究論文によると、最も多い理由は「約束不履行」、すなわち支払う意思はあるものの口座残高不足や手続き漏れといった、いわゆる「うっかり」によるものが全体の約9割(89.57%)占めると報告されています 。これは日本においても、多くの滞納が意図的なものではなく、初期段階での適切なコミュニケーションによって解決できる可能性が高いことを示唆しています。
韓国の共同住宅における滞納原因を分析した研究論文によると、最も多い理由は「約束不履行」、すなわち支払う意思はあるものの口座残高不足や手続き漏れといった、いわゆる「うっかり」によるものが全体の約9割(89.57%)占めると報告されています 。これは日本においても、多くの滞納が意図的なものではなく、初期段階での適切なコミュニケーションによって解決できる可能性が高いことを示唆しています。
しかし、催促に応じないケースや、経済的困窮、所有者との連絡不能といった深刻なケースも存在するため、管理組合としては、あらゆる事態を想定した毅然としつつも計画的な対応体制を構築しておく必要があります。
滞納がもたらす深刻な影響
たとえ少額であっても、滞納の放置は管理組合に深刻な影響を及ぼします。
●管理組合の財政圧迫: 日常の清掃や点検、小規模な修繕といった管理業務は、管理費収入によって賄われています。滞納が続くと、これらの費用が不足し、サービスの質が低下する恐れがあります。
●他の組合員への不公平感: 不足した費用を補填するために、他の組合員の管理費等を値上げせざるを得ない状況も考えられます。これは真面目に支払っている組合員の負担を増大させ、不公平感や住民間の対立を生む原因となります。
●資産価値の低下: 財源不足により、計画されていた修繕が実施できなくなると、建物の老朽化が進行し、マンション全体の資産価値が低下します。
●コミュニティの毀損: 滞納者への対応を巡る意見の対立は、住民間の信頼関係を損ない、円滑なコミュニティ運営の障害となり得ます。
滞納対応の3つのチェックポイント
貴方の管理組合では、滞納に対して有効な手を打てているでしょうか。以下の3つのチェックポイントで、現状の体制を確認してみてください。
チェックポイント①:管理規約は明確か?
滞納督促のすべての根拠となるのが管理規約です。規約が曖昧であれば、いざという時に有効な手を打てません。最低限、以下の点が明確に規定されているか確認してください。
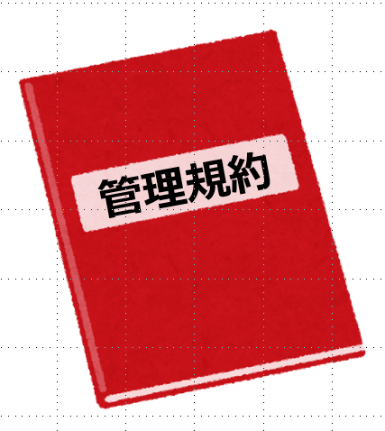 ●遅延損害金の定め: 管理費等を滞納した場合、未納金に対して年利何%の遅延損害金を課すのかを明記します。これは滞納の抑止力となるだけでなく、実際に請求する際の法的根拠となります。利率は管理組合で定めることができますが、標準管理規約では年利14.6%を上限の目安としています。
●遅延損害金の定め: 管理費等を滞納した場合、未納金に対して年利何%の遅延損害金を課すのかを明記します。これは滞納の抑止力となるだけでなく、実際に請求する際の法的根拠となります。利率は管理組合で定めることができますが、標準管理規約では年利14.6%を上限の目安としています。
●費用の請求: 督促状の送付費用(特に内容証明郵便など)や、弁護士に依頼した場合の弁護士費用、訴訟費用などを滞納者に請求できる旨を規定します 。この規定がなければ、たとえ裁判で勝訴しても、かかった費用を管理組合が負担することになり、ひいては他の組合員に負担を強いる結果となってしまいます。
これらの規定は、国土交通省が示す「マンション標準管理規約」に準拠するものです。まずは自組合の規約を確認し、必要であれば規約改正を検討することが、滞納対策の第一歩です。
チェックポイント②:督促体制は明確か?
滞納が発生した際に、「いつ」「誰が」「どのように」対応するかがルール化されていますか。場当たり的な対応は、公平性を欠き、問題を深刻化させる原因となります。
●管理会社に委託している場合:
管理委託契約書の内容を精査し、管理会社がどこまでの督促業務を担うのかを明確に把握しておく必要があります。「令和5年度マンション総合調査」では、滞納者への措置として
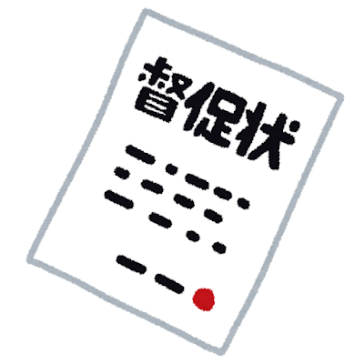 65.2%の管理組合が「文書等による催促」を行っていると回答しており、これが最も一般的な初期対応であることがわかります 。しかし、その頻度や内容(普通郵便か、電話連絡も含むか等)が契約上どうなっているかを確認し、管理会社と組合の役割分担を明確にしておくべきです。
65.2%の管理組合が「文書等による催促」を行っていると回答しており、これが最も一般的な初期対応であることがわかります 。しかし、その頻度や内容(普通郵便か、電話連絡も含むか等)が契約上どうなっているかを確認し、管理会社と組合の役割分担を明確にしておくべきです。
●自主管理の場合:
理事会内で、会計担当理事を中心に督促の役割分担と手順をルール化することが不可欠です。「滞納発生翌月の理事会で担当者がリストを報告し、初期督促を行う」「2ヶ月滞納で理事長名での督促状を送付する」といった具体的なフローを定め、議事録に残しておくことで、担当者の交代があっても一貫した対応が可能になります。
●チェックポイント③:法的措置への移行ルールは明確か?
初期の督促で解決しない場合、どのタイミングで法的措置へ移行するかの基準はありますか。感情的な判断や、対応の先延ばしは禁物です。
「滞納期間が6ヶ月を超えた場合」や「催告状を無視された場合」など、理事会として法的措置の検討を開始する具体的なトリガーをあらかじめ定めておくことが望ましいです。これにより、場当たり的な対応を防ぎ、公平性を担保できます。
冒頭ご紹介しました「令和5年度マンション総合調査」によれば、支払請求等の訴訟(5.9%)や少額訴訟(3.8%)といった法的措置に踏み切った管理組合も存在します。法的措置は最終手段ではありますが、実際に多くの組合が活用している有効な選択肢です。主な手段は以下の通りです。
●支払督促: 裁判所書記官が金銭の支払いを命じる手続き。簡易・迅速。
●少額訴訟: 請求額60万円以下の場合に利用可能。原則1日で審理が終わる。
●通常訴訟: 請求額が大きい場合や争点が複雑な場合。
●競売申立て(区分所有法第59条): 共同の利益に反する行為として、最終的に区分所有権の競売を請求する強力な手段。
どの手続きを選択するかは、滞納額や状況に応じて弁護士などの専門家と相談して決定することが重要です。
予防こそが最善の策
問題発生後の対応だけでなく、滞納を未然に防ぐ仕組みづくりが最も効果的です。
●口座振替の原則化: 支払忘れを防止する最も確実な方法です。
●管理費等の重要性の周知: 総会や広報誌で、管理費等の使途や滞納がもたらす影響について定期的に情報発信し、組合員の当事者意識を高めます。
まとめ:ルールと契約による「仕組み化・半自動化」を目指す
 管理費等の滞納問題は、担当する理事の心理的負担が非常に大きい業務です。だからこそ、個人の努力や感情に頼るのではなく、対応をルールや契約で「仕組み化」し、可能な限り「半自動化」することを目指すべきです。
管理費等の滞納問題は、担当する理事の心理的負担が非常に大きい業務です。だからこそ、個人の努力や感情に頼るのではなく、対応をルールや契約で「仕組み化」し、可能な限り「半自動化」することを目指すべきです。
今回提示した「①規約の明確化」「②督促体制の明確化」「③法的措置ルールの明確化」は、まさにそのための土台作りです。規約という絶対的なルールを整備し、管理会社との契約で督促業務を定義し、法的措置への移行基準を設けることで、滞納対応は属人的な業務から、組合のルールに基づくシステム的な業務へと変わります。
この「仕組み化」こそが、理事の負担を軽減し、公平で継続的な滞納対策を可能にするのです。それが管理組合の健全な財政運営と、マンション全体の資産価値を守ることにも繋がります。
(マンション管理士&税理士 大浦智志)