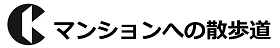マンション管理組合の財務会計(第五十六歩)
■数値で見るマンション修繕積立金クライシス
第3回:迫りくる負債~築年数と「一戸あたり、おおよそ83万円」の借金が示す真実~
 マンション管理士&税理士の大浦です。
マンション管理士&税理士の大浦です。
前回は、積立金の値上げが住民のライフステージといかに衝突するかをシミュレーションしました。今回は、その値上げすらも最終解決策とならず、多くの管理組合が「借金」という名の重荷を背負わされている実態を、国土交通省の最新データに基づき、数値で明らかにしていきます。
【抵抗の心理―なぜ合意形成は進まないのか】
まず、なぜ多くの管理組合が借入れという事態に追い込まれるのか、その入り口である「値上げの停滞」について触れておきます。 前回解説した通り、住民の家計が厳しい時期に値上げが重なることに加え、行動経済学でいう「損失回避」の心理も働きます。人は利益を得る喜びよりも、同額の損失を被る苦痛を心理的に2倍から2.5倍も強く感じるとされています。これが「将来の安心」という利益よりも、「現在の負担増」という損失への強い抵抗感を生む一因となっています。
前回解説した通り、住民の家計が厳しい時期に値上げが重なることに加え、行動経済学でいう「損失回避」の心理も働きます。人は利益を得る喜びよりも、同額の損失を被る苦痛を心理的に2倍から2.5倍も強く感じるとされています。これが「将来の安心」という利益よりも、「現在の負担増」という損失への強い抵抗感を生む一因となっています。
【築年数と共に増加する「借金のあるマンション」】
値上げの合意形成が難航したり、値上げ額が不十分だったりした場合、管理組合はどうなるのでしょうか。国土交通省の「令和5年度マンション総合調査」は、その厳しい現実を示しています。調査によれば、築年数が古いマンションほど、修繕工事のための借入金を抱えている割合が明確に高くなっています。
・1979年以前竣工(築45年以上): 19.3%
・1990~99年竣工(築25~34年): 14.9%
・2010年以降竣工(築14年以下): 5.9%
この数字が意味するのは、今日の新しいマンションも、適切な手を打たなければ、築30年、40年後には5つに1つが借金を抱える未来が待っているということです。これは、個々の管理組合の努力不足というより、構造的な問題が時間と共に顕在化している証拠と言えます。
【一戸あたり、おおよそ83万円の負債:借金漬けの実態】
では、その借金の規模はどの程度なのでしょうか。同調査によると、借入れのある管理組合の平均残高は4,969万円にのぼります。
この「約5,000万円」という数字を、より身近な一戸あたりの負担に換算してみましょう。ここで、より実態に近い数字を把握するため、全体の平均戸数ではなく中央値を採用します。同調査によれば、総戸数の中央値は「51~75戸」の区分に含まれることから、より代表的な戸数として60戸を想定して試算します。
 すると、一戸あたりの借入負担額は、おおよそ83万円(4,969万円÷60戸)となります。
すると、一戸あたりの借入負担額は、おおよそ83万円(4,969万円÷60戸)となります。
このおおよそ83万円という負債は、住民の家計に直接影響します。仮にこの金額を一般的な融資期間である10年で返済する場合、低金利で計算しても月々約7,200円の支払いが新たに発生します。これは、値上げされた修繕積立金に「上乗せ」される形でのしかかってくる、重い負担です。
 【まとめ】
【まとめ】
今回は、多くのマンションが「値上げの停滞」の先に、「借金」という現実に直面していることを、具体的な数値で示しました。特に、古いマンションほど借金割合が高まり、その負担額は「一戸あたり、おおよそ83万円」にも達するという事実は、すべての管理組合にとって他人事ではありません。
次回は、そもそもマンションの積立金制度が、なぜこのような危うさを抱えているのか。企業の資産管理との違いから、その思想的背景を解き明かします。(第4回へ続く)
(マンション管理士&税理士 大浦智志)
以上
【執筆者プロフィール】
大浦智志(おおうら さとし)
コネクトコンサルティング株式会社 代表取締役
税理士法人アイム会計事務所 社員税理士
元最大手管理会社勤務というキャリアを活かし、不動産管理や事業承継に関するコンサルティングを展開。自身もオーナー2世の税理士として、実務と理論を兼ね備えたアプローチに定評あり。著述活動やセミナー講師としても活躍中。
・主な資格:税理士、マンション管理士
・コネクトコンサルティング株式会社URL:https://writtenoath.com/