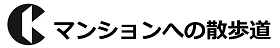マンションと法(第五十一歩)
■マンションを巡る現状と課題②
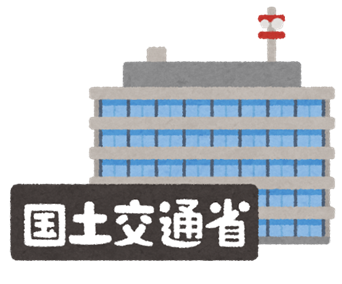 前回に続き、マンションの管理適正化・再生円滑化等を推進するための総合的な施策の方向性についての議論のとりまとめについて見ていきます。
前回に続き、マンションの管理適正化・再生円滑化等を推進するための総合的な施策の方向性についての議論のとりまとめについて見ていきます。
その中でも、今回は、当該とりまとめにおいて記載されている当面取り組むべき施策の方向性を見ていきます。
とりまとめは、総論として、新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、マンションの管理適正化・再生円滑化等を図ることが必要であるとして、取り組むべき施策の方向性を提示しています。
まず、マンションの管理適正化を促す仕組みの充実として、①管理計画認定制度の拡充等、②管理
業者管理者方式への対応が挙げられています。

 ①管理計画認定制度の拡充等については、新築時に分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組みを導入すべきであるとされています。また、管理状況が適正であるか否かについては外観等から判断することが困難であることから、管理計画認定を見える化するための措置を講ずるべきとしています。その具体例としては、エントランスに掲示できる認定証やステッカーの発行や管理組合の意向に応じて、マンションの管理に関する詳細な情報についても公表し、比較検討することが容易となる仕組みを検討すべきであるとされています。適正な管理を行うマンションが評価される仕組みを通じて、管理組合による自主的な適正管理を促すことは重要なことといえます。次に、②管理業者管理者方式への対応については、管理業者が管理者を兼ねる場合には、潜在的に管理組合と管理業者との間で利益相反が生じるおそれが生じるので、管理者受託契約に係る重要事項の区分所有者への説明や、自己取引や関連会社との取引を行おうとする際の区分所有者への事前説明を義務付ける等の措置を講じることが提案されています。また、当該方式を採用した場合には、監事に期待される役割(管理者の業務執行に対する監督)が増大する可能性があることから、監事にはマンション管理士、弁護士、公認会計士などの外部専門家を選任することが望ましいとも指摘されています。
①管理計画認定制度の拡充等については、新築時に分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組みを導入すべきであるとされています。また、管理状況が適正であるか否かについては外観等から判断することが困難であることから、管理計画認定を見える化するための措置を講ずるべきとしています。その具体例としては、エントランスに掲示できる認定証やステッカーの発行や管理組合の意向に応じて、マンションの管理に関する詳細な情報についても公表し、比較検討することが容易となる仕組みを検討すべきであるとされています。適正な管理を行うマンションが評価される仕組みを通じて、管理組合による自主的な適正管理を促すことは重要なことといえます。次に、②管理業者管理者方式への対応については、管理業者が管理者を兼ねる場合には、潜在的に管理組合と管理業者との間で利益相反が生じるおそれが生じるので、管理者受託契約に係る重要事項の区分所有者への説明や、自己取引や関連会社との取引を行おうとする際の区分所有者への事前説明を義務付ける等の措置を講じることが提案されています。また、当該方式を採用した場合には、監事に期待される役割(管理者の業務執行に対する監督)が増大する可能性があることから、監事にはマンション管理士、弁護士、公認会計士などの外部専門家を選任することが望ましいとも指摘されています。
次に、多様なマンション再生ニーズに対応した事業手法の充実として、①区分所有法の見直しへの対応、②多様な建替え等のニーズへの対応が挙げられています。
①区分所有法の見直しへの対応については、区分所有法の見直しにより措置される予定の一棟リノベーション等に対応した新たな決議について、安定的な事業遂行が可能となるよう、対応すべき事業手続を創設するとともに、マンションの再生等の事業が着実に遂行されるよう、ガイドラインやマニュアル等を整備し、技術的な支援務めるとともに、成功事例の横展開や専門家の育成を推進すべきであるとされています。次に、②多様な建替え等のニーズへの対応については、隣接地や底地の権利者との合意形成を促進するための措置を講じることや、マンション建替型総合設計制度について、市街地環境に支障がない範囲で、斜線制限等の高さ制限の特例措置を設けること、建替え等の事業手続を円滑に進めるための所要の措置を講じるべきであることが提案されています。

 最後に、地方公共団体によるマンション管理適正化・再生円滑化への関与の強化・充実として、①地方公共団体の権限強化、②地方公共団体をはじめとした地域全体で支援を行う体制の強化が挙げられています。
最後に、地方公共団体によるマンション管理適正化・再生円滑化への関与の強化・充実として、①地方公共団体の権限強化、②地方公共団体をはじめとした地域全体で支援を行う体制の強化が挙げられています。
①地方公共団体の権限強化については、管理組合による管理のみでは一定の限界があることを踏まえて、マンションの管理状況の把握や勧告後の対応を可能とするような仕組みの創設、外壁剥落等の危険なマンションに対して建替え等を行うことについて地方公共団体から能動的に関与できるように権限を強化すべきことなどが提案されています。②地方公共団体をはじめとした地域全体で支援を行う体制の強化については、地方公共団体の担当者向け研修を行うなどして、地方公共団体の体制の強化に向けた支援を行うべきとされています。また、地方公共団体がマンション管理組合への支援を行う民間団体を登録できる仕組みを導入することで、情報共有を円滑にして、連携の強化を図ることや、マンション管理等に関連する専門家の育成を推進し、地域全体でマンションの管理組合を支援する体制を強化するべきことが提案されています。
(弁護士 豊田秀一)